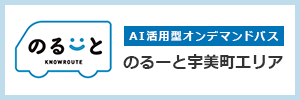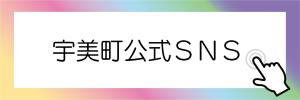本文
9月1日は防災の日です
防災の日とは、台風、大雨、地震などのすべての災害について認識を深め、それらの災害に対処する備えをいま一度考える日であり、昭和35年に制定されました。これは10万人以上の死者・行方不明者を出した、「関東大震災」が大正12年9月1日に発生したことや、大雨・台風などの被害が8月から9月にかけて多いことが由来となっています。
町民の皆さまにおかれましては、日頃よりあらゆる災害に対し、意識し、備えておられるとは思いますが、防災の日を通じて、あらためて災害への心構えや備えについて考えていただける日になれば幸いです。
さて、今年になってからも全国各地で様々な災害が発生しています。1月に発生した日向灘の地震や6月から続くトカラ列島近海での地震活動など、地震大国日本では、いつ発生するかわからない地震と向き合っていかなければなりません。
また、風水害においても、8月9日からの大雨により、県内各地で被害が発生しました。被害に遭われた方々の一日も早い復旧と復興を願うばかりです。宇美町においては、大雨により倒木や側溝からの雨水吹き上げなどが発生いたしましたが、幸い人的被害や住宅被害はなく大事には至りませんでした。
しかし、テレビなどで報道される災害の様子を見ると、明日はわが身かもしれないということを常に考え、日頃から災害に対する備えを十分にしていく必要があると改めて感じます。
大規模な災害が発生した際は、公的機関も打撃を受け、行政や消防、警察などのいわゆる公助となる支援や救助活動に遅れが生じる場合があります。そんなときに重要となってくるのが、自助及び共助となり、自分の身は自分で守るという自助の精神や、災害時には隣近所や自治会などの相互に助け合いを行う共助が多くの命を救います。阪神・淡路大震災の際には、公助による救出は数パーセントとなっており、残りの方は瓦礫の中から自力で脱出した方や、家族や隣人に救助された方が多かったそうです。
このように、災害時における自助・共助とは自分や家族の命を守る重要な考え方であり防災意識のあるべき姿だと思います。近年では、少子高齢化や人口減少などの社会情勢から、昔ほど地域住民同士のつながりが深くはなく、若い方の自治会離れなど厳しい状況となっています。生活リズムや働き方など様々な生活スタイルがある現代ですが、有事の際に、みんなで助け合うということはいつの時代も変わらないことだと思います。防災をきっかけに地域の方と顔見知りになり、自治会や地域行事に参加してみるのはいかがでしょうか。
自助や共助の大切さについてお伝えいたしましたが、町といたしましても、大災害に備え、災害用資機材の準備や食糧・水などの備蓄、いざというときに活躍する職員を育成するための災害対応能力向上研修や訓練の実施など、様々なことに取り組んでいます。また、各自治会やコミュニティでの防災訓練や自主防災組織設立に向けた支援などについても引き続き行っていきたいと思います。
備えに上限はないからこそ、手を緩めることなく今後も災害に強い宇美町を目指し、安心安全なまちづくりに努めてまいります。