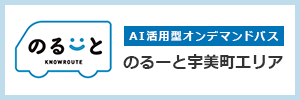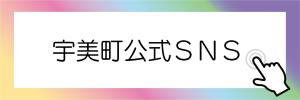本文
療養給付について
病院にかかる時
日本では、安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険加入者はかかった医療費のうち、年齢に応じて以下の割合で一部負担金を支払います。
ただし、入院中の差額ベッド代などは保険給付の対象となりませんので、全額自己負担となります。
| 年齢 | 自己負担割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 | 町が実施している子ども医療からの給付もあり、 3歳以上は一定額の負担、3歳未満は無料で受診できます。 |
| 義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 2割または3割(※) | 70歳の誕生月(1日生まれは前月)に自己負担割合が記載された「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。 |
※【2割負担】 ・・・ 下記以外の方
【3割負担】 ・・・ 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~75歳未満の国保被保険者がいる方
ただし、70歳以上の方の年収合計額が下記のときは、申請により、負担割合が2割負担に変わることがあります。
・単身世帯で年収383万円未満
・2人以上の世帯で合計年収520万円未満
※昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様になります。
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えていた場合、申請して、認められると限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。
宇美町では、対象者の方へ診療月のおよそ3ヶ月後に通知をお送りしています。
<申請の時必要なもの>
・通知文書
・国民健康保険証
・該当月の領収証原本(確認後、返却します)
・世帯主名義の通帳
・世帯主及び受診者全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※医療機関窓口に「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口で支払う金額が世帯毎の自己負担限度額までになります。「限度額認定証」の交付を受けるためには、事前に申請が必要です。
(1)70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 区分 | 所得要件 (旧ただし書所得) |
自己負担限度額(月額:円) | |
| 3回目まで | 4回目以降(※) | ||
| ア | 901万円超え | 252,600円+ (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
| イ | 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+ (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
| ウ | 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+ |
44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給があった場合に適用。
◇70歳未満の人の高額療養費を算定する際◇
(a)同じ月内で、ひとりの方が2つ以上の病院にかかったとき、あるいは、同じ世帯内で複数の人が病院にかかったとき、それぞれ21,000円以上の自己負担をした場合は、それらを足し合わせることができます。21,000円未満のものについては、高額療養費の算定に加えることはできません。
(b)調剤薬局で調剤の医療費を支払われた分については、処方した医科の診療の一環として考えますので、医科と調剤薬局で支払った自己負担を足して、21,000円以上になった場合は合算の対象となります。
(2)70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
70歳以上の方は、かかった医療費の1割または2割(一定以上の所得の方は3割)の負担で医療が受けられます。同一月内に下表の限度額を超えて自己負担額を支払った場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。
宇美町では、高額療養費に該当した場合、診療月の約3か月後にお知らせしています。通知が届いた場合、お手続きしてください。
<申請の時必要なもの>
・通知文書
・国民健康保険証
・該当月の領収証
・世帯主名義の通帳
・世帯主及び受診者全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
|
所得区分 |
外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
|
1 現役並み 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) ○4回目以降の場合は、140,100円 |
|
|
2 現役並み 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ○4回目以降の場合は、93,000円 |
|
|
3 現役並み 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ○4回目以降の場合は、44,400円 |
|
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 ○4回目以降の場合は、44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
|
住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
15,000円 |
|
なお、一般、住民税非課税世帯の8月~翌年7月の年間外来限度額は144,000円です。
※【4回目以降の場合】とは、過去12カ月に3回以上「外来+入院(世帯)」の限度額を超えて、高額療養費の支給が4回目の支給に該当する場合です。
高額療養費の申請手続きの簡素化について
令和3年5月から宇美町国民健康保険の高額療養費の支給対象となる被保険者の負担を軽減することを目的として、
実質的な申請を初回時のみとし、登録した口座に高額療養費を自動的に振り込む、申請手続きの簡素化を行っております。
高額療養費に該当した場合、通知をお送りしていますので、通知が届いたらお手続きしてください。
健康保険で受けられる医療
- 診察
- 病気や怪我の治療
- 検査、レントゲン撮影等
- 治療に必要な薬や注射
- 入院
※訪問看護についても医師の指示のもとで利用する場合には保険対象となることがあります。
保険対象とならない医療
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正、美容整形
- 健康診断、集団検診、予防接種
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
- 仕事上の病気、けが(労災保険の適用)
※その他、けんかや泥酔、または犯罪を犯した場合や故意による病気や怪我については、給付が制限される場合があります。
入院したときの食事代
医療機関に入院したときの食事代は、一定の金額(標準負担額)を負担することになります。標準負担額については下表のとおりとなります。
入院したときの食事代は、1食につき、次の一定額を負担します。残りは国保が負担します。
| 一般加入者(ア・イ・ウ・エ、現役並み、一般) | 490円 | |
| 住民税非課税世帯 (オ、低所得者2) |
90日までの入院 | 230円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
180円 | |
| 住民税非課税世帯(低所得者1) | 110円 | |
※高額療養費の支給の対象にはなりません。
※住民税非課税世帯等の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保係窓口に申請しましょう。
※低所得者2とは→70歳以上の方でその者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税の世帯
※低所得者1とは→70歳以上の方でその者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税で、その世帯の各所得が0の世帯
※一般とは→低所得者1・低所得者2・現役並み所得者に該当しない方
入院期間が90日を超えたら、申請してください
住民税非課税世帯に該当する方で、入院期間が90日を超えると、食事代が1食あたり、230円から180円に減額されます。申請月の翌月初日からの認定となります。申請が遅れたときでも、限度額適用認定証をお持ちである場合に限り、差額支給の申請ができます。
▼長期該当の申請に必要なもの
・保険証
・領収書(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
・標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
・委任状(別世帯の方が申請に来られる場合)
・世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真が添付された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)※顔写真のないものは2点必要
▼差額の払い戻しに必要なもの
・保険証
・領収書(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
・標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
・預金通帳
・委任状(別世帯の方が申請に来られる場合)
・世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真が添付された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)※顔写真のないものは2点必要
一部負担金の減免について(病院の窓口で支払いに困ったとき)
災害、失業その他特別な事情により、一時的、臨時に病院の窓口で支払いが困難になった場合、申請して認められると、 一部負担金の減額、免除、聴き取る猶予等を受けることができます。
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を負担することになります。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費 |
|---|---|---|
| 一般世帯 | 490円 (一部医療機関では450円) |
370円 |
| 住民税非課税世帯 70歳以上で低所得者2に該当する人 |
230円 | 370円 |
| 70歳以上で低所得者1に該当する人 | 140円 | 370円 |
・療養病床とは急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。
高額介護合算療養費について
国保と介護保険それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して一定額を超えた時は、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費に該当した方に通知しています。
合算した場合の自己負担限度額(年額/8月~7月)(70歳未満)
| 所得要件 | 限度額 | ||
| 住民税課税世帯 | 旧ただし書所得 901万円超 |
212万円 | |
| 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 | ||
| 旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
67万円 | ||
| 旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | ||
合算した場合の自己負担限度額(年額/8月~7月)(70歳以上75歳未満)
| 所得要件 | 限度額 | |
| 課税所得690万円以上 | 212万円 | |
| 課税所得380万円以上 690万円未満 |
141万円 | |
| 課税所得145万円以上 380万円未満 |
67万円 | |
| 一般世帯 | 56万円 | |
| 低所得世帯2 | 31万円 | |
| 低所得世帯1 | 19万円 | |
※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
特定疾病の認定
高額な治療を長い間続ける必要がある次の病気は、同じ医療機関で支払う自己負担限度額は1ヶ月1万円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満の旧ただし書所得が600万円超の方は2万円)になります。該当する方には「特定疾病療養受療証」を発行しますので、申請してください。ただし、認定は申請をした月の1日からになります。
・人工透析を必要とする慢性腎不全
・血友病及び抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
<申請の時必要なもの>
・国民健康保険証
・医師の意見書
・世帯主及び認定を受ける方のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)