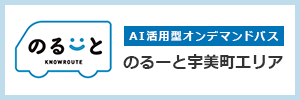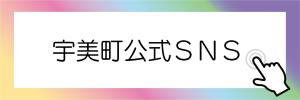本文
限度額適用認定証と高額療養費等のご案内
マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証で受診される方は、限度額適用認定証を取得しなくても、医療機関での支払いが自動的に「高額療養費の限度額」に合わせて設定されます。これにより、高額な医療費がかかっても、限度額を超える支払いは必要ありません。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
資格確認書で受診される方は、限度額適用認定証を取得し、医療機関へ提示しないと高額な医療費を請求される場合があります。
「資格確認書」と「限度額適用認定証」を病院に提示すると、窓口での支払いがA表またはB表に記載された限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。この認定証を受けた方は、入院時の食事代も減額されます。
- 食事代や差額ベッド代など、保険診療外の費用は、限度額適用の対象外となります
- 同一世帯に前年(または、申請年度の7月までに申請する場合は前々年)の所得が未申告の方がいる場合、正しく区分判定ができません。収入がない場合でも、必ず申告してください。
- 70歳以上の方で、B表の負担区分が「一般世帯」または「現役並み所得者」で、課税所得が690万円以上の方は、認定証の申請は不要です。
<申請に必要なもの>
- 資格確認書
- 世帯主および認定証が必要な方のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 手続きに来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要 - 委任状(別世帯の方が手続きに来られる場合)
※現在、国民健康保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、有効期限が過ぎても引き続き必要な場合は、8月中に再申請をお願いいたします。
限度額適用認定証 申請用紙 [Excelファイル/37KB]
【対象者】
以下に該当する方で、1ヶ月の医療費が高額になる方
- 69歳以下の国民健康保険加入者
- 70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、B表の【○必要】に該当する方
※外来診療でも限度額適用認定証を利用できます。
医療費は月単位で計算されます。外来は個人単位、入院は世帯単位で計算されます。
また、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは対象となりません。
70歳未満の方の自己負担限度額
医療費は、月単位、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別々)に計算されます。
また、自己負担限度額に達しない場合でも、同一月内に同一世帯で各医療機関に21,000円以上支払った自己負担額が複数あるときは、それらを合算して計算されます。(世帯合算)
なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。
入院時の食事代や保険診療ではない差額ベット代等は対象となりません。
| 所得区分 | 1ヶ月の自己負担限度額 | ||
| 3回目まで | 4回目以降(※) | ||
|
住民税課税世帯 |
旧ただし書所得(※1) 901万円超 |
252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円 + (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
| 旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
| 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
※過去12か月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当があった場合の限度額
※1 旧ただし書所得(国保被保険者ごとに計算します)=総所得金額等(※2) - 基礎控除(43万円) ※2 総所得金額等・・・前年の所得と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰り越し控除は控除しない。
70歳~74歳の方の自己負担限度額
B表
|
所得区分 |
1ヶ月の自己負担限度額 |
限度額適用・ 標準負担額認定証 |
||
|
外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
|||
| 現役並み所得世帯 |
課税所得690万円以上 |
252,600円 ○医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ○4回目以降の場合は、140,100円 |
×不要 | |
|
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円 ○医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ○4回目以降の場合は、93,100円 |
○必要 | ||
|
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円 ○医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ○4回目以降の場合は、44,400円 |
○必要 | ||
|
一般世帯 |
18,000円 ※8月~翌年7月の年間上限 144,000円 |
57,600円 ○4回目以降の場合 44,400円 |
×不要 | |
|
低所得世帯2 |
8,000円 |
24,600円 |
○必要 | |
|
低所得世帯1 |
15,000円 |
○必要 | ||
・現役並み所得世帯とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯です。ただし、 70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合、旧ただし書所得(※1)の合計が210万円以下である場合は申請することにより「一般世帯」の区分になります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった方は、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の場合、旧ただし書所得の合計が210万円以下である場合は、申請により「一般世帯」の区分になります。
・低所得世帯2とは
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
・低所得世帯1とは
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯です。
※1 旧ただし書所得(国保被保険者ごとに計算します)=総所得金額等(※2) - 基礎控除(33万円) ※2 総所得金額等・・・前年の所得と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰り越し控除は控除しない。
・一般世帯とは
低所得者1、低所得者2、現役並み所得者に該当しない世帯です。
医療費が高額になったとき
同じ月内にA表またはB表の限度額を超えて医療費を支払った場合、申請により超過分が支給されます。
宇美町では、高額療養費に該当した場合、診療月の約3か月後に通知をお送りします。通知が届きましたら、必要な手続きを行ってください。
<申請に必要な書類>
- 通知文書
- 資格確認書、資格情報のお知らせ
- 該当月の領収書
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主および受診者全員のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 手続きを行う方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
高額療養費の申請手続きの簡素化について
高額療養費の見込みが発生した場合、以下の3点をお送りします
- 国民健康保険高額療養費支給(見込み)のお知らせ
- 国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書
- 申請手続き簡素化についての説明文
お送りした「国民健康保険高額療養費振込先口座確認書・承諾書」に必要事項を記入し提出していただくことで、記入された口座が受取口座として登録され、今後発生する高額療養費は原則として登録口座に自動的に振り込まれます。
なお、提出時期によっては登録が間に合わない場合や、自動振込停止要件に該当する場合があります。このような場合、高額療養費が発生した月ごとに改めて申請手続きを行っていただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
高額介護合算療養費について
国民健康保険(国保)と介護保険のそれぞれで適用される限度額を超えて、年間の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。宇美町では、高額介護合算療養費に該当した方に対して、該当通知をお送りしていますので、通知が届いた場合はお手続きください。
合算した場合の自己負担限度額(年額/8月~7月)(70歳未満)
| 所得区分 | 限度額 | ||
| 住民税課税世帯 | 旧ただし書所得 901万円超 |
212万円 | |
| 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 | ||
| 旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
67万円 | ||
| 旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | ||
合算した場合の自己負担限度額(年額/8月~7月)(70歳以上75歳未満)
| 所得区分 | 限度額 | ||
| 現役並み所得世帯 | 課税所得690万円以上 | 212万円 | |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | ||
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | ||
| 一般世帯 | 56万円 | ||
| 低所得世帯2 | 31万円 | ||
| 低所得世帯1 | 19万円 | ||
所得区分についてはB表下の説明を参照ください。
※低所得世帯1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
特定疾病療養受療証について
長期間にわたって高額な治療を受ける必要がある次の病気の方は、同じ医療機関での自己負担限度額が1ヶ月1万円となります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満かつ旧ただし書所得が600万円を超える場合は、自己負担限度額が2万円となります。
該当する方には「特定疾病療養受療証」を発行しますので、申請をお願いします。認定は、申請した月の1日から適用されます。
対象となる病気は以下の通りです:
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血友病、および抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む、厚生労働大臣が定めた者に限る)
<申請に必要な書類>
- 資格確認書、資格情報のお知らせ
- 医師の意見書
- 世帯主および認定を受ける方のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 手続きを行う方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)