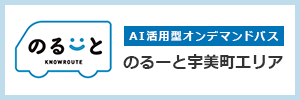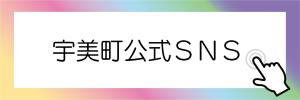本文
大野城跡
日本最古の古代山城 国指定特別史跡 大野城跡
大野城跡は、福岡県宇美町・太宰府市・大野城市にまたがる四王寺山にある全長約8kmに及ぶ広大な古代山城で、宇美町にその城内の大半が所在します。
日本の古代史において重要な史跡であることから、国の特別史跡に指定されています。国の特別史跡とは、国宝レベルの扱いと思って頂ければ分かりやすいかと思います。
大野城跡は、別名、四王寺山と言われますが、古くは大野山と呼ばれていました。その大野山になぜ山城が築かれたのでしょうか。その理由を述べるには、当時の社会情勢を少し説明する必要があります。
大野城跡はなぜつくられたのか
7世紀の初め頃、朝鮮半島では、高句麗・百済・新羅の三国が互いに戦争を繰り返していました。
660年、新羅は中国を統一した唐の援助を受けて百済に攻め入り、百済は滅亡してしまいます。百済の遺臣は、大和朝廷(当時の日本)に救援を求め、大和朝廷はそれに応じ、663年、百済を救援するため、朝鮮半島に出兵します。これが、教科書にも登場する有名な「白村江の戦い」です。
救援に向かった大和朝廷でしたが、唐・新羅連合軍に敗れてしまいます。この結果、連合軍の日本侵攻が想定されたため、664年に大宰府政庁(九州の政治拠点)を防衛するための水城跡を造り、その後、665年に大野城が築城されるのです。つまり、大野城跡は、大宰府政庁が攻撃された時に備えた籠城のためのお城であったといえます。
大野城はお城といっても、近世の天守閣などがあるお城や中世の山城と違い、土塁(城壁)と石垣で山を囲んだ古代の山城です。土塁と石垣で囲まれた城内には、建物跡(役所的機能をもつ建物や食糧庫・武器庫など)、城門、水場(井戸・池)、水門などが造られています。
土塁

土塁というのは、敵の侵入に備えた土でできた壁のことです。質の違う土を数cmごとに積んでは叩きしめるという工法で巨大な土塁を造っています。このような工法を「版築(はんちく)」といいます。
土塁は四王寺山の尾根をとり巻く様に造られています。谷間など、宇美町側と太宰府市側は、二重の土塁が設けられています。これら土塁と石垣の総延長は、約8kmにも及ぶ長大なものです。
石垣

尾根は土塁で防御していますが、谷部など大雨で土塁が崩壊する可能性がある箇所では石垣を造っています。
石垣は現在、5箇所見つかっています(百間石垣・大石垣・北石垣・小石垣・水ノ手口石垣)。
なかでも、宇美町側から県民の森センターに向かう途中の右側にある百間石垣は、全長約180mにも及ぶ立派な石垣です。
城門

城には、必ず出入口が必要です。現在、8箇所で城門跡が発見されています(宇美口城門・太宰府口城門・坂本口城門・水城口城門・原口城門・北石垣口城門・小石垣口城門・観世音寺口城門)。
平成19年度の北石垣口城門の発掘調査では「鉄製軸受金具(てつせいじくうけかなぐ)」が発見されました。
建物跡
 【増長天礎石群】
【増長天礎石群】
お城の中には、多くの建物があったと推定できる礎石建物跡が70棟以上見つかっています(主城原礎石群・村上礎石群・尾花礎石群・増長天礎石群・猫坂礎石群・広目天礎石群・八ツ並礎石群・御殿場礎石群)。
尾花礎石群のそばに焼米ヶ原と呼ばれている場所があり、そこでは炭化した当時のお米を拾うことができることから、多くは食糧保管庫であったと考えられています。
その後の大野城跡
大規模な土木工事によって造られた大野城でしたが、半島から連合軍が攻めてくることはありませんでした。
ところが、その後、新羅が日本を呪って祈祷しているという噂が広まったため、774年、大野城跡に四天王寺(四王寺)というお寺が建てられます。現在、四王寺山という名前で呼ばれている由来は、奈良時代に建てられたこのお寺と考えられます。
現在、四王寺山には、四天王である「毘沙門天」「広目天」「持国天」「増長天」と呼ばれる地名が残っています。これも四天王寺の名残といえるでしょう。
お寺の創建当初の建物跡などは発見されておらず、その実態は謎に包まれたままなのです。
アクセス
| 大野城跡 | |
| 連 絡 先 | 福岡県立四王寺県民の森管理事務所<外部リンク>〒811-2105 糟屋郡宇美町大字四王寺宇207番地 Tel 092(932)7373 |
| 交通 | 西鉄バス「県民の森入口」から約4km(徒歩約50分) 西鉄「大宰府」駅から約4km(徒歩約50分) 駐車場150台、大型バス10台 |
| 開園時間 | 4月1日~9月30日/AM9時00分~Pm6時00分 10月1日~3月31日/AM9時00分~Pm5時00分 |
| 休 園 日 | 月曜日(この日が祝祭日の場合は、その後の直近の平日) 12月29日~1月3日 |