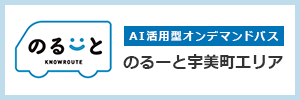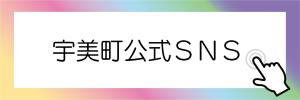本文
宇美八幡宮本殿・拝殿及び幣殿・神門が国登録有形文化財(建造物)に登録されます
宇美町初の国登録有形文化財の誕生
令和7年7月18日(金曜日)に開催された国の文化審議会は、宇美八幡宮の本殿・拝殿及び幣殿(へいでん)・神門の3件について、国登録有形文化財(建造物)に登録するよう、文部科学大臣に答申しました。
この結果、官報告示を経て、国登録有形文化財(建造物)に登録されます。
宇美町では、初の国登録有形文化財の誕生になります。
【国登録有形文化財とは】
建築物などのうち、原則として建設後 50 年を経過したもので、(1)国土の歴史的景観に貢献しているもの、(2)造形の規範となっているもの、(3)再現することが容易でないもの、以上の条件のいずれかに該当することが登録の基準となります。
クスの杜に囲まれた宇美八幡宮境内
【登録物件】
(1)本殿

明治19年建築。木造入母屋造(いりもやづくり)檜皮葺(ひわだぶき)、建築面積62平方メートル。
造形の規範となる建造物として評価されました。
(2)拝殿及び幣殿

明治19年建築(明治32年・昭和33年増築)
木造切妻造(もくぞうきりづまづくり)銅板葺(どうばんんぶき)、建築面積100平方メートル。
大工棟梁は、原七右衛門持好。明治32年に幣殿を増築し、昭和33年に拝殿の向拝及び両側面部を増築しています。
拝殿後方に両下造(りょうさげづくり)銅板葺の幣殿を接続しており、増築によって変化ある屋根構成が優美な社殿です。
歴史的景観に貢献する建築として評価されました。
(3)神門

昭和33年建設。木造切妻造銅板葺の八脚門。間口7.9m。
設計は黒木利三郎、施工は中村時次郎。
軒反り(のきぞり)が優美であり、参道を見通す開放的な造りであり、境内の軸線を強調しています。
造形の規範となる建造物として評価されました。