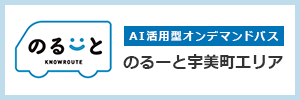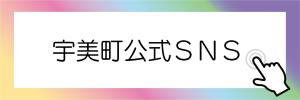本文
個人町県民税(住民税)の概要
住民税とは
一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼びます。
令和6年度からは森林環境税(国税)1,000円が加わりました。
個人の住民税は、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に対して、均等の額によって税金を負担する「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」が課税されます。
宇美町で住民税がかかる方
その年の1月1日現在、宇美町に居住している方に、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて税金がかかります。
宇美町に居住していない場合でも、町内に家や事業所、事務所がある場合は「均等割」のみが課税されます。
住民税がかからない方
均等割も所得割もかからない方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が一定金額以下の方
非課税判定 315,000円 × ( 本人 + 扶養の人数 ) + 189,000円 + 100,000円
※ただし、扶養の人数が0人の場合、非課税判定の基準額は415,000円です。
所得割がかからない方
前年の総所得金額が一定金額以下の方
非課税判定 350,000円 × ( 本人 + 扶養の人数 ) + 320,000円 + 100,000円
※ただし、扶養の人数が0人の場合、非課税判定の基準額は450,000円です。
税額
均等割の税額
年間5,500円
(町民税3,000円+県民税1,500円(県民税のうち500円は福岡県森林環境税)+森林環境税(国税)1,000円
所得割の税率
町民税:6%、県民税:4%
所得割の計算
所得割の税額は一般に次の方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
所得金額とは
所得割の税額計算の基礎となる所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことよって算定されます。
住民税は前年中(1月1日~12月31日)の所得を基準として計算されます。
たとえば令和7年度の住民税では、令和6年1月1日から令和6年12月31日の所得金額が基準となります。
所得控除とは
所得控除は、その方に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その方の実情に応じた税負担を考えるために所得金額から差し引くものです。
代表的なものとして、配偶者控除や扶養控除、医療費控除などがあります。
納税の方法
個人の住民税の納税の方法には普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税していただきます。
普通徴収
事業所得者などの住民税は、納税通知書(納付書)によって毎年6月に各個人に通知され、6月・8月・10月・翌年の1月の4回にわけて納税していただきます。
町税の納付についてはこちらをご覧ください。「納付方法」
給与からの特別徴収
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、宇美町から給与の支払者を通じて各個人に通知され、給与の支払者が毎月の給与支払の際に、その方の給与から住民税を天引きして、天引きした税金を翌月の10日までに宇美町に納入します。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で納税していただきます。
特別徴収の手続に必要な届出書は、下記よりダウンロードできます。
税に関する申請書等ダウンロード書式一覧
年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている方)の住民税は、公的年金から特別徴収されます。
ただし、町外へ転出、税額変更、年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となります。納付書(普通徴収)をお送りするので、金融機関等で納付してください。
※ 当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である場合、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を越える場合等は、対象から除外されます。
※障害年金や遺族年金については、非課税所得(税金のかからない所得)となっていますので、特別徴収の対象とはなりません。
4月・6月・8月の特別徴収の金額について(仮徴収)
年間の徴収税額の平準化を図るため、4月・6月・8月に特別徴収する金額を「前年の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とする」ことになっています。
その年度の税額が6月に確定しますので、4月・6月・8月の特別徴収額を差し引いた残額を10月・12月・翌年の2月に特別徴収します。
特別徴収を開始する年度の徴収方法
公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額を、6月・8月に納付書(普通徴収)で納税していただきます。
残りの2分の1は、10月・12月・翌年の2月に年金から特別徴収します。