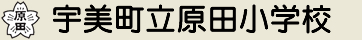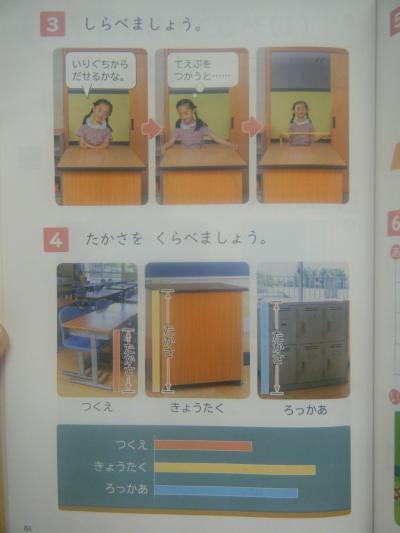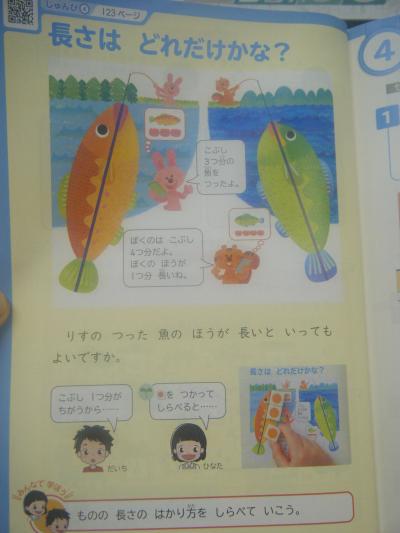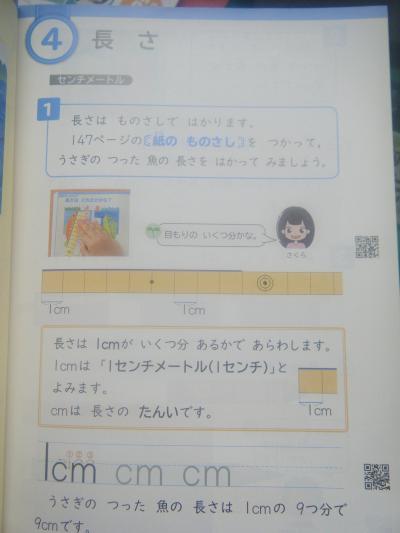9月22日 原田小学校の風景~そんなに水筒ばかり持ってきてどうするの?!
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月22日更新
白い紙袋を持ってきている子どもがいたので見せてもらいました。

ん?水筒みたいなのが3つ。
でも、よく見ると普通の水筒も肩にかけているじゃありませんか。
「なんで、こんなに水筒みたいなのばかり持ってきてるの?」
「算数の学習で使うんです。」
「ああっ、『かさ』の学習ね。」
「はいそうです。」
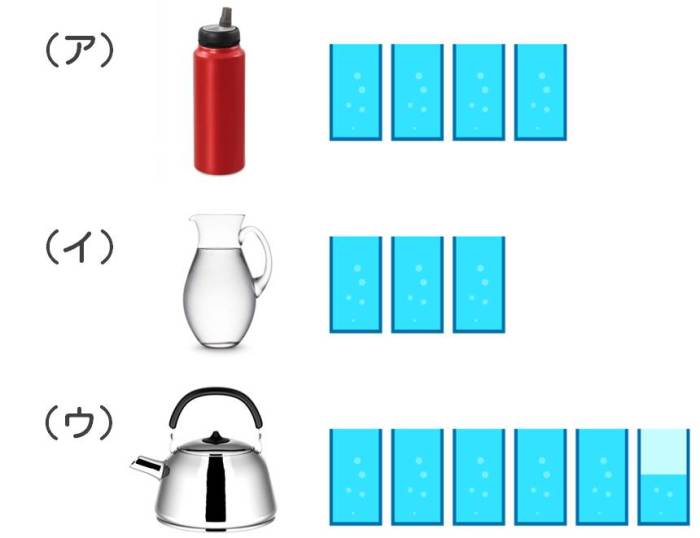
量の学習は、「長さ」「かさ」「広さ」「重さ」「時間」・・・と見てすぐに比べやすいものから学習していくのです。
子どもがそれぞれの量をどのように学習していくか、「長さ」を例に説明します。
1.比較したいものを直接比較する「直接比較」を学習します。
2.テープなどに置き換えて比較する「間接比較」を学習します。
3.消しゴムや鉛筆を基準にそのいくつ分で数値化して比較する「任意単位比較」を学習します。
4.最後に世界共通の単位をもとに数値化して比較する「普遍単位比較」を学習します。
6.量を使った足し算、引き算を学習します。(量の保存性)
このように、ほかの量でも同じように学習を進めていくことで、「量」の概念が育っていくのです。
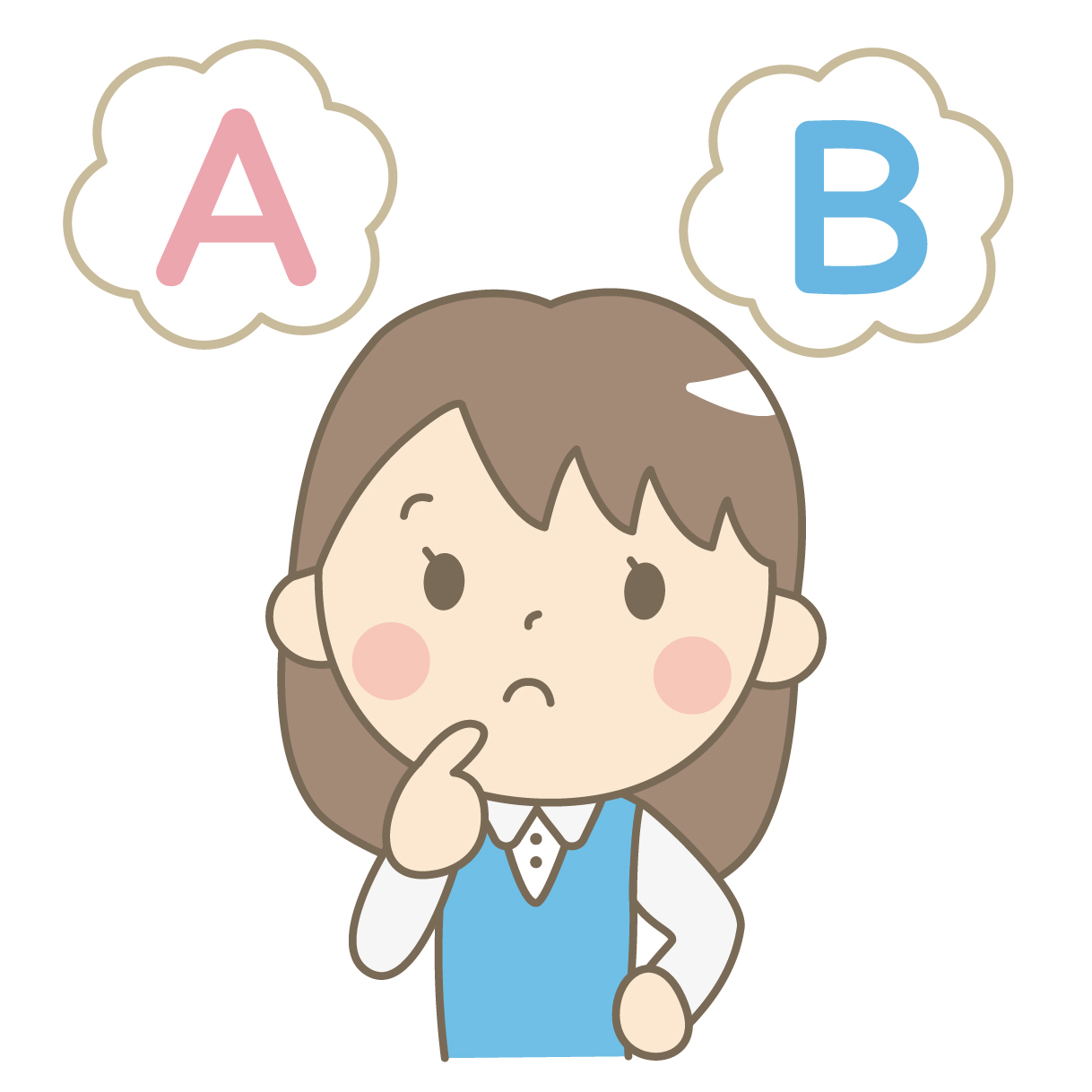
「ねぇ、このジャガイモを持ってみて。何グラムぐらいあると思う?」
「このテーブル隣の部屋に持って行きたいんやけど、ドアのところ通るかな?」
「このコップとこのグラスとどっちがたくさん入ると思う?」

学校だけでなく家庭でも日常的に「量」の概念を意識する声かけをしていただくと、子どもの知的好奇心を刺激し脳の成長を促しますので、是非実践されてください。(A.A)